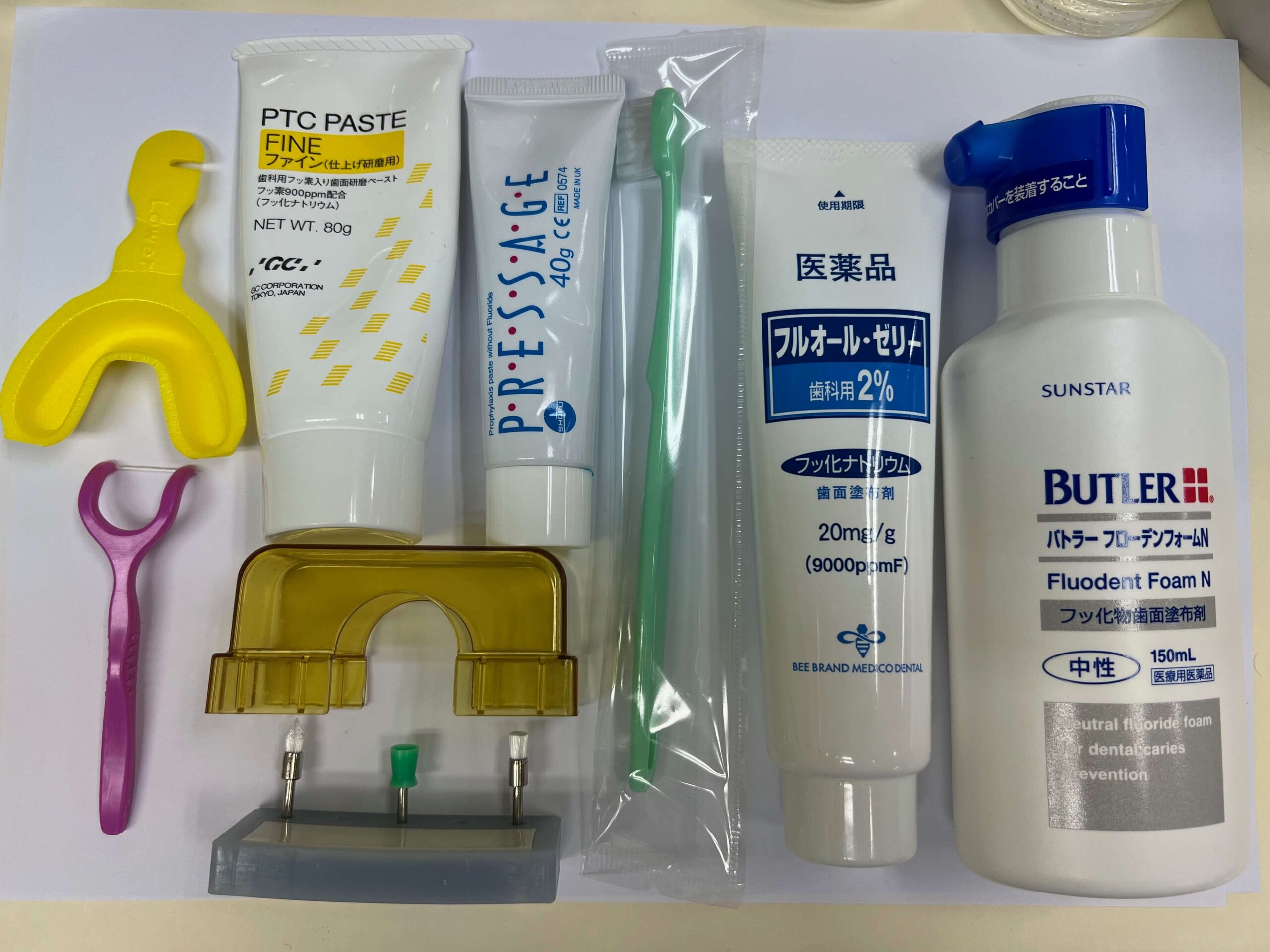当院では、小児歯科専門医として、お子さまの口腔機能を正常に保つための『口腔機能管理』および『MFT(筋機能療法)』を実施しています。これらは、咀嚼・嚥下・発音・呼吸といった基本的な口腔機能をサポートし、健全な成長と健康を促すための重要な取り組みです。
口腔機能管理とは?
口腔機能管理とは、食べる・飲み込む・話す・呼吸するといった口腔の基本的な機能を適切に発達・維持するための取り組みです。特に小児期には、これらの機能が成長期に応じて発達していくため、早期の管理が将来の健康に大きく寄与します。
- 対象となる主な問題
- 口呼吸
- 舌癖(舌の不適切な位置や動き)
- 咀嚼や嚥下の異常
- 発音の不明瞭さ
- 目的
- 正しい咬み合わせの形成
- 健全な顔面骨格の発育
- 全身の健康との連携(呼吸や姿勢の改善)
MFT(筋機能療法)とは?
MFT(Myofunctional Therapy)は、舌・唇・頬の筋肉のトレーニングを行うことで、口腔機能を正常に整える治療法です。お子さまの不良習癖や口腔機能の問題を改善し、歯並びや咬み合わせに良い影響を与えます。
- MFTの具体的なアプローチ
- 舌の正しい位置を習得する練習
- 口を閉じる力を強化するエクササイズ
- 嚥下(飲み込み)のトレーニング
- 発音や呼吸の改善
- 期待できる効果
- 口呼吸の改善と鼻呼吸の促進
- 顔のバランスの改善と歯並びの安定化
- 長期的な歯列矯正の効果を高める
口腔機能の発達が健康に与える影響
お子さまの成長期における口腔機能の発達は、次のような全身的な健康に影響を与えます:
- 正しい咬み合わせ
- 食べ物をしっかり噛むことできるようになります。
- 鼻呼吸による健康効果
- 鼻呼吸が定着することで、睡眠の質や免疫力が向上します。
- 発音や言語の発達
- 正しい舌の使い方が、明瞭な発音を助けます。
当院の取り組み
当院では、お子さまの口腔機能管理とMFTに力を入れています。以下のような特徴をもっています:
- 個別診断とトレーニング
- お子さま一人ひとりの口腔機能を詳しく評価し、オーダーメイドのトレーニングプランを作成します。
- 楽しく続けられる指導方法
- お子さまがゲーム感覚で取り組めるトレーニングを提供します。
- 家庭でのフォローアップ
- ご自宅で簡単に実践できるエクササイズを保護者に指導します。
- 定期的な経過観察
- 成長に合わせたトレーニングの調整とフォローアップを行います。
保護者の皆さまへのメッセージ
お子さまの口腔機能は、健康な成長に欠かせない重要な要素です。特に、小さな問題が将来的な歯並びや健康に影響を及ぼす可能性があります。当院では、専門医として保護者の皆さまと連携し、安心して取り組める環境を整えています。お気軽にご相談ください。
参考:口腔機能とは
口腔機能とは?その役割と重要性
今回は「口腔機能」についてお話しします。あまり耳慣れない言葉かもしれませんが、実は私たちが毎日当たり前のように行っている「噛む」「飲み込む」「話す」などの動きに深く関わっている大切な機能です。特にお子さまの健やかな成長にとって、口腔機能は欠かせない役割を果たしています。
では、口腔機能とは具体的にどんなものか、なぜ重要なのかを詳しくご紹介していきましょう。
口腔機能とは、お口の中やその周囲の筋肉、舌、歯などが協力して働くことで、食べ物を噛む・飲み込む・話す・呼吸するといった基本的な動作を支える一連の仕組みのことを指します。これらの機能が正しく発達し、うまく働いていることで、子どもは栄養をしっかり摂取でき、言葉の発達もスムーズになります。
なぜ口腔機能がそんなに大切なのでしょうか?
その理由は、食べる力と言葉の力が、子どもの心と体の発育に直結しているからです。たとえば、しっかり噛んで食べることで消化吸収が良くなり、体が元気になります。また、舌や口の周りの筋肉がしっかり動くことで、発音がきれいになり、コミュニケーション力も高まります。つまり、口腔機能は「生きる力」を支える基本のひとつと言えるのです。
具体的な例を挙げると、赤ちゃんが成長する過程で、最初は母乳やミルクを飲むだけだったのが、少しずつ離乳食を食べられるようになり、そのうちおしゃべりも始めます。この一連の流れすべてに、口腔機能の発達が関わっています。噛む力、飲み込む力、舌や唇を動かす力がバランスよく育つことで、子どもは安心して食事ができ、楽しく会話ができるようになります。
もしこの口腔機能にトラブルがあると、食べることや話すことが苦手になり、それが栄養不足やコミュニケーションの遅れにつながってしまうこともあります。そのため、口腔機能の発達状況を理解し、適切にサポートしていくことがとても大切です。
今回は、そんな口腔機能について詳しくお話していきます。次の章では、成長期の子どもにとって口腔機能がどのように関わっているのかをご紹介します。
子どもの成長と口腔機能の関係
子どもの健やかな成長には、口腔機能の発達が大きく関わっています。結論から言うと、口腔機能の発達は、体の発育や言葉の習得、心の成長にも深く影響を与えます。なぜなら、食べ物をしっかり噛むこと、上手に飲み込むこと、正しく発音することは、子どもの日常生活そのものを支える基本動作だからです。
具体的に、口腔機能が子どもの成長にどう関わっているのか、次の3つの観点から見ていきましょう。
1. 栄養摂取と体の成長
まず、噛む・飲み込むといった基本動作がしっかりできることで、子どもはさまざまな食材をバランスよく食べられるようになります。噛む力が弱い、飲み込みが苦手だと、柔らかいものばかりを選んでしまい、栄養が偏る原因になります。噛むことで唾液の分泌も促進され、消化吸収がスムーズになり、体の成長を助けます。特に幼少期は、体を作る大切な時期。口腔機能がしっかりしていることは、栄養摂取の基盤を支える重要なポイントです。
2. 言葉の発達とコミュニケーション
舌や唇、頬の筋肉がしっかり動くことで、発音がスムーズになり、言葉を正しく覚えられるようになります。言葉の発達は、子どもが自分の思いや考えを伝えるために不可欠です。たとえば、舌の動きがうまくコントロールできないと、特定の音が出しにくくなり、発音が不明瞭になってしまいます。口腔機能が整っていると、発音の正確さが向上し、コミュニケーション能力の発達を助けます。
3. 呼吸と姿勢の安定
口腔機能は、呼吸や姿勢とも密接な関係があります。口をポカンと開けてしまう習慣がある子は、口呼吸になりがちですが、これは口腔機能の発達が遅れているサインかもしれません。口呼吸が続くと、姿勢が崩れたり、歯並びが悪くなったりするリスクがあります。また、口腔機能がしっかりしていると、鼻呼吸がスムーズにでき、体全体のバランスも整います。
このように、口腔機能は体の成長、言葉の発達、呼吸や姿勢の安定といった、子どもの健やかな成長に欠かせない役割を担っています。そのため、成長期の子どもたちの口腔機能がしっかり発達しているかを見守り、必要に応じてサポートしていくことが大切です。
次の章では、口腔機能が低下するとどのような影響があるのかを詳しくお話ししていきます。
口腔機能低下がもたらす影響
口腔機能がしっかり働いていないと、どのような影響が出てくるのでしょうか?結論から言うと、口腔機能の低下は、食事・会話・呼吸といった日常生活の質を下げ、成長や健康に悪影響を与える可能性があります。そのため、早期に気づき、適切な対応をすることが大切です。
では、なぜ口腔機能の低下がそれほど問題なのか、そして具体的にどのような影響があるのかを詳しく見ていきましょう。
1. 食事に関する問題
口腔機能が低下すると、噛む力や飲み込む力が弱まり、食べられる食材が限られることがあります。柔らかいものばかりを食べる習慣が続くと、咀嚼筋(そしゃくきん:噛むための筋肉)が十分に使われず、さらに噛む力が低下する悪循環に陥ります。その結果、栄養が偏り、成長に必要なエネルギーや栄養素が不足することもあります。また、しっかり噛まないまま飲み込んでしまうことで、胃腸に負担がかかり、消化不良を起こすリスクも高まります。
2. 発音やコミュニケーションへの影響
口腔機能が低下すると、舌や唇、頬の筋肉の動きが不十分になり、発音が不明瞭になったり、言葉が出にくくなることがあります。特に子どもの場合、言葉の発達段階でこのような問題が生じると、周囲の人とうまくコミュニケーションが取れず、自己表現に苦手意識を持つ原因になることも。これは、友達関係や学校生活にも影響を与え、心理的なストレスにつながる可能性があります。
3. 呼吸や姿勢への影響
口腔機能が低下すると、口を閉じる力が弱くなり、口呼吸が習慣化することがあります。口呼吸は、鼻呼吸に比べて空気中のほこりやウイルスをろ過する働きが弱く、風邪をひきやすくなる原因になります。また、口呼吸が続くと、舌の位置が下がり、歯並びや顔の骨格にも影響を与える可能性があります。さらに、呼吸が浅くなることで姿勢が悪くなり、全身のバランスにも悪影響が及ぶことがあります。
このように、口腔機能の低下は、身体的な健康だけでなく、精神的な成長にも深く関わっているのです。そのため、普段の生活の中で「噛むのが苦手そう」「発音が不明瞭」「口がポカンと開いている」などのサインに気づいたら、早めに歯科医院など専門機関に相談することが大切です。
次の章では、最近注目されている「口腔機能発達不全症」について、詳しくご紹介していきます。
口腔機能発達不全症について知ろう
最近、子どもの口腔機能に関する問題として注目されているのが「口腔機能発達不全症(こうくうきのうはったつふぜんしょう)」です。これは、噛む・飲み込む・話す・呼吸するなどの口腔機能が、年齢相応に発達していない状態を指します。特に子どものうちにこうした機能が適切に育たないと、成長過程でさまざまな不調や困りごとが生じる可能性があります。
では、口腔機能発達不全症とはどのようなものか、なぜ重要なのかを詳しく見ていきましょう。
口腔機能発達不全症の特徴
口腔機能発達不全症は、口腔機能の一部、もしくは複数の機能がうまく働いていない状態で、そのままにしておくと、歯並び、噛み合わせ、食事や会話など、日常生活に支障をきたすことがあります。たとえば、以下のような特徴が見られる場合は、口腔機能発達不全症の可能性があります。
- 食べ物をしっかり噛まずに飲み込んでしまう
- 舌をうまく使えず、発音が不明瞭になる
- 口がいつもポカンと開いている
- 鼻呼吸が苦手で口呼吸が多い
- よだれが出やすい
- 飲み込みが苦手で食事に時間がかかる
これらは、口腔周囲の筋肉や舌の動き、呼吸機能がうまく連携していないことが原因で起こります。
なぜこの症状が問題なのか
結論として、口腔機能発達不全症を放置してしまうと、栄養状態や言葉の発達、顔の骨格形成、さらには心理的な成長にまで影響が及ぶ可能性があるため、早期発見と対処が重要です。特に、歯並びや噛み合わせに問題が出ると、矯正治療が必要になることもありますし、発音が不明瞭だと学校生活で困ることも増えてしまいます。
また、呼吸の仕方が正しくないことで、姿勢が崩れたり、睡眠の質が低下したりすることもあります。これらは、体全体の健康状態にも影響を与えるため、口腔機能の問題は見逃してはいけないのです。
口腔機能発達不全症の診断と対応
この症状は、歯科医院や耳鼻科、小児科などで行われる検査や診察を通じて判断されます。診断の際には、食べ方、話し方、呼吸の仕方、口の周りの筋肉の動きなどを総合的に確認します。必要に応じて、トレーニングや指導、または矯正治療などを行い、子どもの口腔機能をサポートしていきます。
次の章では、家庭でできる口腔機能を育むためのケア方法について、具体的にご紹介していきます。口腔機能発達不全症を予防するためにも、日常の中でできることを積み重ねていきましょう。
健やかな口腔機能を育むための家庭でのケア
口腔機能の発達を支えるためには、歯科医院でのサポートも大切ですが、日常生活の中で行う家庭でのケアがとても重要です。結論から言うと、毎日の生活習慣の中で、正しい食べ方や呼吸、発音の練習を意識することで、口腔機能は自然と育まれていきます。
なぜ家庭でのケアが重要かというと、口腔機能は食事や会話、呼吸といった日常のあらゆる場面で使われているため、その環境や習慣が発達に大きな影響を与えるからです。では、具体的にどのようなケアができるのか、わかりやすくご紹介します。
1. 正しい姿勢で食事をする
まず、食事の際の姿勢はとても大切です。椅子に深く腰掛け、足裏がしっかり床や足置きについた状態で食べることで、体幹が安定し、噛む力や飲み込む力が正しく使えるようになります。姿勢が崩れていると、舌や口の周りの筋肉が正しく動かず、噛む力が弱くなってしまうことがあります。特に小さなお子さんは、足がぶらぶらしないよう、足置き台などを活用すると良いでしょう。
2. よく噛んで食べる習慣をつける
食事では、一口30回を目安にしっかり噛むことを意識しましょう。噛むことで顎の筋肉が鍛えられ、咀嚼力が向上します。噛む回数が少ないと、柔らかいものばかりを好むようになり、口腔機能の発達が遅れてしまいます。硬すぎる食材を無理に与える必要はありませんが、適度に噛みごたえのある野菜やお肉、乾物などを取り入れて、自然と噛む回数を増やす工夫をしましょう。
3. 鼻呼吸を意識する
普段の呼吸も口腔機能に大きく関わっています。鼻呼吸を習慣づけることで、口をしっかり閉じる力が育ち、口腔内の乾燥や口呼吸によるトラブルを防ぐことができます。子どもがテレビを見ているときや遊んでいるときに、口がポカンと開いていないかチェックし、声をかけてあげることも大切です。もし口呼吸が習慣化している場合は、寝るときの体勢や環境を整えたり、耳鼻科で相談するのも一つの方法です。
4. 発音や舌の動きを意識した遊び
歌を歌ったり、早口言葉を練習したり、舌を使った遊びも、口腔機能を育む良い方法です。例えば、舌を上下左右に動かす運動や、口をすぼめたり大きく開けたりする動作は、口の周りの筋肉を鍛えるのに効果的です。これらはゲーム感覚で取り入れると、楽しく続けられます。
このように、家庭でできるちょっとした工夫や習慣が、子どもの口腔機能の発達をしっかりサポートします。無理のない範囲で、毎日の生活の中に取り入れていきましょう。
次の章では、歯科医院でできる口腔機能のサポートについて、詳しくご紹介していきます。家庭でのケアと専門的なサポートを組み合わせることで、より健やかな成長を目指していきましょう。
歯科医院でできる口腔機能のサポート
家庭でのケアに加えて、歯科医院での専門的なサポートも、子どもの口腔機能を健やかに育てるうえでとても大切です。結論から言うと、歯科医院では口腔機能の発達状況を的確にチェックし、必要に応じたトレーニングやアドバイスを受けられるため、成長に合わせた適切な支援が期待できます。
なぜ歯科医院でのサポートが必要なのかというと、口腔機能の発達は、家庭では気づきにくい細かな部分に影響を及ぼすことがあるからです。専門家の視点で診察することで、早い段階で課題を見つけ、適切な対応ができるようになります。
1. 口腔機能のチェック
歯科医院では、定期検診の際に口腔機能の状態をチェックしています。例えば、歯並びや噛み合わせ、舌や唇の動き、呼吸の仕方、発音の状態などを総合的に観察します。こうしたチェックを通じて、噛む力が弱い、飲み込みにくい、口呼吸が多いといった問題点が早めにわかるため、成長に合わせたアドバイスが受けられます。
2. 必要に応じたトレーニングの提案
口腔機能に課題が見つかった場合、歯科医院ではそれぞれの子どもに合ったトレーニングや指導を提案します。例えば、舌の動きを良くするための運動や、唇を閉じる力を強化するトレーニングなどが行われることがあります。これらの指導は、お子さんが無理なく楽しく続けられるよう、遊びの要素を取り入れながら実施されることが多いです。
3. 食べ方・飲み込み方の指導
食事の際の噛み方や飲み込み方についても、適切な方法を指導しています。例えば、舌の位置や顎の動きを意識しながら食べること、口をしっかり閉じて飲み込むことなど、正しい動作を習得できるようサポートします。こうした指導は、家庭でも継続できるよう、保護者の方にもわかりやすく説明されます。
4. 必要に応じた矯正治療の提案
歯並びや噛み合わせが原因で口腔機能に問題がある場合、矯正治療が必要になることもあります。この場合も、成長に合わせたタイミングや方法を歯科医師が判断し、無理のない計画を立てていきます。早期に対応することで、より自然な形での改善が期待できます。
このように、歯科医院では専門的な視点で口腔機能の発達を見守り、必要に応じたサポートが行われています。家庭でのケアと合わせて、定期的に歯科医院を利用することで、子どもの口腔機能をしっかりと育んでいきましょう。
次の章では、日常生活で簡単に取り入れられる口腔機能を育むトレーニング方法について、具体的にご紹介していきます。
日常生活でできるトレーニング方法
口腔機能を高めるには、特別な器具や複雑な練習が必要だと思われがちですが、実は日常生活の中で簡単に取り入れられるトレーニングがたくさんあります。結論から言うと、遊び感覚でできるシンプルな動作を毎日少しずつ続けることが、口腔機能の発達にとても効果的です。
では、具体的にどのようなトレーニングがあるのか、ご家庭でできる方法をわかりやすくご紹介します。
1. 口をしっかり閉じる練習(リップトレーニング)
口の周りの筋肉を鍛えるには、まず「唇をしっかり閉じる」力を育てることが大切です。
おすすめなのが「割り箸トレーニング」です。軽く割り箸を唇だけで挟み、手を使わずに10秒キープする練習をします。慣れてきたら少し時間を延ばしてみましょう。これによって、口を閉じる筋力が育ち、口呼吸の予防にもつながります。
2. 舌のトレーニング
舌の動きをスムーズにすることは、発音や飲み込みに大きく関わります。
簡単にできる方法としては、「舌を左右に動かす」「上の前歯の裏をなぞる」「舌で頬の内側をぐるぐるなぞる」などの動きがおすすめです。鏡の前で「べー」と舌を出して動かすだけでも楽しいトレーニングになります。遊びながら行えるのがポイントです。
3. 呼吸トレーニング
鼻呼吸を促すには、「ふーっ」と息を長く吐く練習が効果的です。
たとえば、紙で作った風車やしゃぼん玉を使って、息を吹いて回したり、しゃぼん玉を飛ばしたりする遊びは、楽しく呼吸筋を鍛えることができます。また、「鼻で息を吸って、ゆっくり口から吐く」練習も、リラックス効果があり集中力の向上にもつながります。
4. よく噛むことを意識した食事
食事中の「噛む」動作も、大切なトレーニングのひとつです。
一口30回を目標にしっかり噛むことで、咀嚼筋(そしゃくきん)が鍛えられ、唾液の分泌も促進されます。食材は噛み応えのあるものをバランスよく取り入れましょう。お子さんと一緒に「どっちが多く噛めるかな?」と競争してみるのも楽しい工夫です。
5. 発音を意識した遊び
「早口言葉」や「しりとり」、「歌を歌う」などの遊びを通じて、発音や舌の動きを自然に鍛えることができます。
特に早口言葉は、口の動きを速く正確にする練習として非常に効果的です。「あかまきがみ、あおまきがみ…」といった定番のものから、オリジナルで作ってもOKです。
このように、日常生活の中には、口腔機能を育てるヒントがたくさんあります。無理に頑張るのではなく、楽しみながら毎日少しずつ続けることが大切です。
次の章では、ここまでのまとめとして「終わりに」をお届けします。口腔機能への理解を深め、日常に取り入れるヒントとしてお役立てください。
終わりに
今回は「口腔機能とは?」というテーマで、その役割や重要性、そしてご家庭でできるケアや歯科医院でのサポートまで、幅広くお伝えしました。改めてお伝えしたいのは、口腔機能はお子さまの健康な成長を支える大切な土台であり、食べる・話す・呼吸するといった毎日の動作に深く関わっているということです。
しっかり噛む力や飲み込む力、正しい発音、スムーズな呼吸は、身体の発育だけでなく、心の発達やコミュニケーション能力の向上にもつながります。また、これらがバランスよく育まれていることで、お子さまが自信を持って生活し、健やかに成長していけるのです。
しかし、口腔機能のトラブルは見逃されやすいものでもあります。「食事に時間がかかる」「口がポカンと開いている」「発音が不明瞭」など、日常のちょっとしたサインに気づくことが、早めの対処につながります。家庭でのケアとともに、定期的な歯科医院でのチェックも取り入れて、お子さまの口腔機能をしっかり見守っていきましょう。
私たち歯科医院では、お子さま一人ひとりの成長に合わせたサポートを行っています。気になることがあれば、どうぞお気軽にご相談ください。お子さまの未来を一緒に支えていけるよう、スタッフ一同、心を込めてサポートしてまいります。
参考:MFT(口腔筋機能療法)とは?
今回は「MFT(口腔筋機能療法)」についてお話していきます。聞き慣れない言葉かもしれませんが、これは子どもの口周りの筋肉を整え、正しい呼吸や嚥下(飲み込み)、発音、舌の位置などを習得するための大切なトレーニングです。
結論から言うと、MFTは「お口の癖」を改善し、歯並びや顎の成長にも良い影響を与えることが期待される機能的なアプローチです。
子どもたちの健やかな成長のためには、虫歯の予防や歯磨きだけでなく、「正しく使えるお口」へ導くこともとても重要です。特に近年では、口呼吸や舌の癖など、口腔機能の発達に課題を抱えるお子さんが増えており、その影響が歯並びや姿勢、さらには睡眠の質にまで及ぶことが分かってきました。
MFT(Myofunctional Therapy=筋機能療法)は、こうしたお口周りの機能のアンバランスを改善するために、歯科医院や矯正治療の現場でも活用されるようになってきています。特に小児期は、お口の筋肉や習慣を自然に修正しやすい時期のため、早めのアプローチが非常に効果的です。
例えば、「舌がいつも前に出ている」「口がポカンと開いている」「くちゃくちゃ食べる」といった日常の様子は、お子さんの口腔機能の発達に課題があるサインかもしれません。こうした癖があると、将来的に歯並びや噛み合わせ、発音、顔つきにまで影響を及ぼす可能性があります。
MFTでは、舌の正しい位置を覚えたり、鼻呼吸を意識的に行ったりといったシンプルな動作を、段階的なトレーニングで身につけていきます。これにより、自然な形でお口のバランスが整い、矯正治療の効果を高める補助的な役割を果たすこともあります。
本記事では、このMFTについて、なぜ必要なのか、どんなトレーニングを行うのか、いつ始めるのがベストかなど、親御さんに知っていただきたいポイントを分かりやすく解説していきます。
お子さんのお口の成長に不安を感じている方や、矯正治療を検討中の方にとって、役立つ情報をたっぷりお届けしますので、ぜひ最後までご覧ください。
なぜ子どもにMFTが必要なのか
結論からお伝えすると、子どものうちからMFT(口腔筋機能療法)を行うことで、将来の歯並びや顎の発育、さらには呼吸・姿勢・発音などの成長に関わる多くの問題を未然に防ぐことができます。
その理由は、口腔機能が発達途上である子ども時代が、「正しい使い方を身につけやすい時期」であるからです。成長期の子どもたちの筋肉や骨格は柔軟で、生活習慣やトレーニングの影響を受けやすく、正しい癖が定着しやすいという特徴があります。
たとえば、以下のような日常的な癖は、歯並びや噛み合わせに大きな影響を与えることがあります:
- 口をポカンと開けている(口呼吸)
- 食事中にくちゃくちゃ音を立てる(咀嚼・嚥下の異常)
- 舌がいつも下や前にある(低位舌)
- 発音が不明瞭(構音障害)
- 指しゃぶり、唇をかむなどの口唇癖
こうした癖は、自然に治ることもありますが、多くの場合は放置すると歯並びを悪化させたり、顎の骨の発育に影響したりする可能性があります。また、呼吸に問題があると睡眠の質が下がったり、姿勢が悪くなったりと、全身の発育に関係してくることもあるのです。
MFTは、そうした日常の癖や口腔機能の問題に対して、「どう正しく使うか」を筋肉の訓練で身につける療法です。たとえば、「舌を上あごにつけること」「鼻で呼吸をすること」「唇をしっかり閉じること」といった基本的なことを段階的にトレーニングしていきます。
小児期にMFTを導入することには、次のような利点があります:
- 成長途中の柔軟な身体で改善が早い
- 悪い癖が定着する前に正しい習慣を身につけられる
- 矯正治療の補助となり、治療後の後戻りを防ぎやすくなる
- 親子で取り組みやすく、家庭でも継続できる
また、学校生活や日常生活での「発音が通らない」「疲れやすい」「集中力が続かない」といった悩みも、実は口腔機能のバランスが関係しているケースがあります。そのような背景から、MFTは単なる“歯科的な介入”にとどまらず、「全身の健やかな発育を支える基礎」として注目されています。
子どもの健やかな成長には、歯の健康だけでなく、正しく使えるお口、すなわち“機能の健康”がとても重要です。MFTは、その土台を築く大切な手段のひとつとして、多くの保護者の方に知っていただきたい療法です。
口呼吸とMFTの関係
結論から言えば、口呼吸はお口の筋肉のバランスを崩し、様々な健康リスクを招くため、MFT(口腔筋機能療法)によって鼻呼吸への切り替えを目指すことがとても重要です。
人間の本来の呼吸は「鼻呼吸」です。鼻には空気中のホコリやウイルスをフィルターで除去し、湿度や温度を調整して肺へ届けるという重要な役割があります。しかし、口呼吸が習慣化してしまうと、乾燥した空気が直接のどや肺へ入り込み、風邪をひきやすくなったり、アレルギーや気道の問題を引き起こしやすくなることが知られています。
とくに成長期の子どもにとって、口呼吸は以下のような問題の原因になる可能性があります:
- 歯並びが乱れやすくなる(上顎の発育不全など)
- 顎の成長に悪影響を及ぼす(下顎が後退しやすくなる)
- 睡眠の質の低下(いびき、睡眠時無呼吸症候群のリスク)
- 姿勢の悪化や集中力の低下
- 唇が乾燥しやすい、口臭の発生など
このような状態を予防・改善するために、MFTでは「口を閉じて鼻で呼吸する」ことを中心にトレーニングを行っていきます。たとえば、以下のような方法があります:
- 唇をしっかり閉じる練習(リップトレーニング)
- 舌の正しい位置(上あごのスポット)を習慣づける
- 鼻での呼吸を意識的に行う練習
- 頬や口輪筋の筋力を高めるトレーニング
これらの訓練により、口が自然と閉じられるようになり、口呼吸が減少していきます。さらに、舌が上あごに収まることで上顎の発育が促され、歯が並ぶスペースが確保されやすくなるという利点もあります。
口呼吸は、単なる「癖」として片づけることはできません。実際には、お口の筋肉や姿勢、呼吸器の問題など複合的な要因によって生じていることが多く、早期に対応しなければその影響が長期にわたって続くこともあります。
特に、口が常に開いているお子さん、寝ているときに口が乾いている、いびきをかくといった様子が見られる場合は、MFTによるアプローチが有効である可能性があります。
お子さんの呼吸の状態に少しでも不安がある場合は、歯科医院でのMFT相談を検討してみることをおすすめします。早期に介入し、正しい呼吸習慣を身につけることで、成長を健やかに支えることができます。
MFTで改善が期待できるお口の癖
結論から言うと、MFT(口腔筋機能療法)は、子どもに多く見られるお口の「悪習癖(あくしゅうへき)」を改善することが期待できるトレーニングです。これらの癖は放置しておくと、歯並びや噛み合わせ、発音、さらには顔つきや姿勢にも影響を与えることがあります。
では、具体的にどのような癖がMFTの対象となるのでしょうか。以下のような日常的な癖が代表的です:
- 低位舌(ていいぜつ):舌が常に下の方や前方にある状態。正常な位置は、上あごの前方にある“スポット”と呼ばれる場所です。舌が正しい位置にないと、上顎の成長が妨げられ、歯が並ぶスペースが不足する原因となります。
- 口呼吸:常に口が開いていて、鼻でなく口で呼吸している状態。唇の閉鎖力が弱く、舌の位置も不安定なことが多く、感染症や歯列不正のリスクが高まります。
- 逆嚥下癖(ぎゃくえんげへき):飲み込む際に舌が前に出て歯を押すような動きになってしまう癖。これにより前歯が押し出され、開咬(かいこう:上下の前歯がかみ合わない状態)になりやすくなります。
- 異常嚥下(いじょうえんげ):舌や唇を使って不自然に飲み込む動作。正しい嚥下は、舌を上に持ち上げて喉に送り込む動作で、筋肉の連動が重要です。
- 構音障害(こうおんしょうがい):舌や唇の動きが不十分で、「さ行」や「た行」の音が不明瞭になるなどの発音の問題が見られることがあります。これは舌の使い方や位置の影響が大きいです。
- 唇や舌を噛む、指しゃぶり、爪噛み:こうした癖もMFTの対象であり、筋肉のアンバランスを正すことで改善が期待されます。
これらの癖は一見すると些細に思えるかもしれませんが、日常的に繰り返されることで口腔や顎の発達に持続的な影響を与えていきます。そのため、MFTではそれぞれの癖に応じたトレーニングプランを作成し、子どもに無理のない方法で正しい筋機能を育てていきます。
例えば、低位舌の改善には、舌を上顎に持ち上げる練習を行い、舌筋を鍛えることが中心になります。逆嚥下癖に対しては、嚥下時の正しい動きを鏡の前で練習したり、嚥下反射を誘導するための小道具を使ったりすることもあります。
MFTの魅力は、「成長に合わせて自然な改善が期待できる」という点にあります。子どもは大人に比べて筋肉や神経系の柔軟性が高いため、トレーニングによって習慣そのものを良い方向へと導きやすいのです。
そして、MFTは単なる「矯正の補助」ではなく、根本から「口の使い方」を変えていくアプローチです。だからこそ、見た目の歯並びの問題だけではなく、「正しい機能」と「健やかな成長」を一緒に目指す治療として注目されています。
MFTの具体的なトレーニング方法
MFT(口腔筋機能療法)は、ただの筋トレではなく、「正しいお口の使い方」を習慣づけるための継続的なトレーニングです。ここでは、実際に行われている代表的なトレーニング方法をご紹介しながら、それぞれがどのような目的で行われるのかを詳しくお伝えします。
結論から言うと、MFTのトレーニングは、舌・唇・頬などの筋肉を正しく機能させ、自然と正しい嚥下・呼吸・発音などができるように導いていくものです。トレーニングは1つずつはシンプルですが、毎日の積み重ねが大切で、家庭での取り組みと歯科医院での指導を併用しながら進めていきます。
主なトレーニングの例は以下のとおりです:
1. リップトレーニング(唇の筋力アップ)
唇の閉じる力が弱いと、口呼吸が習慣化しやすくなります。唇をしっかり閉じる力をつけるために、「ストローを唇だけでくわえて引っ張る」「ボタンやコインを唇で挟んで保持する」などの練習を行います。
2. タングアップ(舌の位置の矯正)
舌が常に下にある低位舌の癖を改善するために、舌を正しい位置(上顎のスポット)に置く練習をします。たとえば、舌の先をスポットにつけて数秒間保持する、舌をスポットに当てながら「ポン」と音を出す(ポッピング)といったトレーニングです。
3. タングスライド(舌の柔軟性と可動域向上)
舌を上顎に沿って滑らせる運動で、舌全体の動きを滑らかにし、正しい嚥下に必要な筋肉の協調性を高めます。これは発音や飲み込みの改善にも役立ちます。
4. 嚥下(えんげ)トレーニング
逆嚥下癖がある場合には、嚥下の動作そのものを正しくする練習が必要です。食べ物を口に含んだ状態で舌をスポットにつけたまま唾を飲むような練習や、水を少量含んで正しい飲み込み方を繰り返す練習が行われます。
5. 頬筋・口輪筋トレーニング
ストローでの吸引や、水を口に含んだまま保持する練習、口の中に空気をためて左右の頬に移動させる「ブクブクうがい」のような運動なども、口周りの筋力強化に役立ちます。
これらのトレーニングは、個々の癖や課題に応じて歯科医師や歯科衛生士が内容をカスタマイズし、1日数回の短時間で無理なく継続できるように設計されます。特に子どもにとっては「楽しみながら続けられること」が非常に大切で、シール帳やトレーニングカレンダーを使ってモチベーションを維持する工夫も行われています。
また、定期的に歯科医院でチェックを受けることで、トレーニングの効果や進み具合を確認し、必要に応じて内容を調整していきます。
MFTは単なるトレーニングではなく、「正しいお口の使い方を覚える生活習慣の指導」とも言えます。そのため、日常生活の中でも正しい姿勢や鼻呼吸の意識などが求められることになります。保護者の方の見守りや声かけが、お子さんの成功を大きく後押ししてくれます。
MFTを始めるベストなタイミングと通院の流れ
結論から言うと、MFT(口腔筋機能療法)はできるだけ早い段階から始めることが望ましいです。特に、小学校低学年ごろまでに始めると、お口の筋肉や習慣の修正がスムーズに行える傾向があります。
その理由は、成長期の子どもはまだ筋肉や骨格が柔軟で、生活習慣による影響を大きく受けやすいためです。悪い癖がまだ深く定着していないうちに介入できれば、自然に「正しい使い方」を習得することができ、矯正治療や口腔機能全体の発達に良い影響を与えることが期待されます。
MFTを始める目安
MFTは基本的に、お子さんが指示を理解して行動できる年齢(およそ4~5歳以降)からが目安です。ただし、実際の開始時期は、お口の状態や癖の内容、本人のやる気や協力の度合いによって異なります。以下のようなサインがある場合は、早めに歯科医院で相談されることをおすすめします。
- 口がいつも開いている(口呼吸の可能性)
- 食べるときにくちゃくちゃ音を立てる
- 舌が前に出る・舌足らずな話し方をする
- 寝ているときにいびきをかく
- 指しゃぶりや唇をかむ癖がある
通院の流れとプログラムの進め方
MFTは一度の診察で完了するものではなく、定期的なトレーニングとフォローアップが必要な療法です。以下のような流れで進んでいきます。
1. 初診・評価
まずは歯科医院にて、お口の状態や呼吸、嚥下、発音などの機能評価を行います。視診や問診、場合によっては動画撮影や写真記録などを用いて、お子さんの癖や筋機能の状態を把握します。
2. トレーニング計画の作成
評価結果をもとに、個々のお子さんに適したトレーニング内容を設定します。癖の種類や年齢、性格に応じて、家庭でも無理なく続けられるプログラムを提案します。
3. 定期的な通院とトレーニングの進行
おおよそ月1回のペースでの通院が一般的です。診療では、前回からの進捗確認や、新しいトレーニングの指導を行い、動画や写真で比較しながらモチベーションを保ちます。
4. ご家庭での継続
MFTの成否を大きく左右するのは「家庭での実践」です。歯科医院で学んだトレーニングを、毎日5分〜10分程度で継続し、日常生活の中でも正しい口の使い方を意識づけます。保護者の方の見守りやサポートがとても重要です。
5. 修了・再評価
おおよそ半年〜1年を目安に、癖の改善状況を評価し、必要に応じて修了や延長、あるいは矯正治療への移行などを検討します。
MFTは「短期で終わる治療」ではなく、「生活習慣の再教育」として、長い目で取り組むことが成功のカギです。ですが、その分だけ、お子さん自身が得られるものは非常に大きく、成長期に正しい習慣が身につくことで、歯並びや発音だけでなく、自信や健康面にも良い影響が期待できます。
ご家庭で気をつけたいこととサポート方法
MFT(口腔筋機能療法)は、歯科医院でのトレーニング指導に加え、ご家庭での実践が非常に重要です。結論からお伝えすると、MFTの成功のカギは「日常生活の中での継続とご家族のサポート」にあります。家庭での習慣や環境が、子どもの口腔機能の発達に大きく影響を与えるからです。
ご家庭で気をつけたい習慣や環境
MFTに取り組むお子さんにとって、日常のちょっとした行動や姿勢がトレーニングの効果を左右します。以下の点に注意してみましょう。
- 口が開いている時間が長くないかチェック テレビを見ている時や寝ている時、無意識に口が開いていないか観察してみましょう。口呼吸の癖がある場合は、声かけや、口を閉じやすくするためのリップトレーニング補助具などを活用することもあります。
- 食事の姿勢を整える 足をしっかり床につけ、背筋を伸ばした状態で食事をさせましょう。猫背や横座りなどの不安定な姿勢は、舌や唇、頬の筋肉の正しい使い方を妨げます。
- 噛む回数と食べ物の形態に注意 柔らかい食事ばかりではなく、適度に噛む力が必要なもの(例:野菜スティック、やわらかく煮たお肉など)を取り入れて、咀嚼機能の発達を促しましょう。
- 正しい鼻呼吸の促進 鼻炎などで鼻が詰まっていると口呼吸になりやすくなります。耳鼻科との連携も含めて、常に鼻呼吸ができる状態に整えておくことが理想です。
- 正しい舌の位置を確認 遊びの中やリラックスしている時に、舌が上顎についているかどうかをさりげなくチェックするだけでも違います。「お口の体操しようか?」など声かけをして、ゲーム感覚で促すのも有効です。
おうちでのサポート方法
MFTのトレーニングは、継続がとても大切ですが、子ども自身が毎日黙々と練習するのは難しいこともあります。そこで、保護者の方の関わり方が大きなポイントになります。
- 毎日のスケジュールの中に組み込む 朝の支度前や寝る前など、習慣化しやすいタイミングに組み込み、「◯◯のあとにトレーニングする」という流れを作るとスムーズです。
- できたことをしっかり褒める 「今日は舌を10秒スポットにつけられたね!」など、具体的に褒めることで、子どものやる気がぐんと上がります。褒められることで自信にもつながります。
- トレーニングを一緒に行う 親子で同じ動きをしてみることで、お子さんも楽しく取り組めます。また、正しい動きを一緒に確認することができ、より効果的な練習になります。
- 記録やカレンダーで“見える化” シール帳やトレーニングカレンダーを使って、練習した日を可視化すると達成感が得られやすくなります。「今日も頑張ったね」と振り返る時間を大切にしましょう。
無理せず、でも継続を
お子さんによってはモチベーションに波があったり、トレーニングを嫌がることもあるかもしれません。そのときは無理に押しつけず、一旦間を置いたり、楽しい雰囲気で再開できる工夫をしてみてください。
MFTは「治療」ではありますが、「親子で一緒に取り組む健康づくりの習慣」として考えると、取り組みやすくなります。保護者のやさしい声かけと見守りが、お子さんの口腔機能の健やかな成長を大きく後押ししてくれるのです。
終わりに
ここまで、MFT(口腔筋機能療法)について、その目的や必要性、改善が期待できる癖、具体的なトレーニング内容、そしてご家庭でのサポートの重要性について詳しくお伝えしてきました。
お子さんの「歯並び」や「発音」、「食べ方」、「口が開いている」などのちょっとした気になるサイン。その背後には、実は口腔機能のアンバランスが隠れていることがあります。そうした問題を早期に見つけ、「正しいお口の使い方」を学ぶことは、お子さんの一生の健康の土台をつくる大切な一歩です。
MFTは、特別な機械や薬を使うわけではなく、子ども自身が自分の体を使って「気づき」「修正」し、習慣として身につけていく療法です。その過程では、保護者の方の支えや共感がとても大きな力になります。時には根気が必要なこともありますが、お子さんの未来の健康や自信につながると考えると、非常に価値のある取り組みだと言えるでしょう。
また、MFTは「矯正治療のサポート」としても効果が期待されており、歯並びの治療を始める前や治療中、さらには治療後の安定にも寄与することがあります。大切なのは、見た目の美しさだけでなく、「機能的に正しい口の状態」を目指すこと。その視点を持つことで、将来的なトラブルの予防にもつながります。
「こんな癖、うちの子にもあるかも」「もしかして口呼吸している?」と気になった方は、ぜひ一度歯科医院にご相談ください。専門的な評価とアドバイスを受けることで、早めの対策が可能になります。
お子さんの笑顔と健康を守るために、ぜひこの機会に「MFT」という選択肢を知っていただき、日々の生活の中に取り入れてみてください。